こんにちは。関西産研のHP担当です。
2025年10月23日(木)に開催された「第52回 産業精神保健講演会」(大阪精神科診療所協会主催・ハイブリッド開催)に参加しましたので、その様子を報告いたします。本講演会には関西産研も後援団体として関わっており、シンポジウムでは関西産研幹事の黒木和志郎先生が登壇されました。
基調講演では関西産研会長である深井恭佑先生より、演者である安田由華先生(フォレスター生きる育む輝くメンタルクリニック梅田本院)のご紹介があり、安田先生から「うつ病治療ガイドラインと最近の薬物療法の動向」についてご講演がありました。エビデンスに基づく薬物療法の基本から、実臨床に即した処方選択や留意すべき点など、精神科医がどのような判断プロセスで治療を組み立てているのかが非常に分かりやすく整理されました。参加者は、日頃「処方の背景が見えにくい」と感じている点を補う形で、多くの気づきを得られたように思います。
続くシンポジウムでは、座長の関西産研である清原達也先生の進行のもと、「精神科処方と職場支援・安全配慮」をテーマに、より実務的な議論が展開されました。その中で黒木和志郎先生は、「産業医の視点から見た精神科処方〜職場の支援や安全配慮の実際〜」と題して登壇し、産業医の役割についてお話しされました。黒木先生が繰り返し強調されたのは、産業医は病名や症状といった“疾病性”だけに目を向けるのではなく、「上司の指示に従わない」「遅刻・欠勤が続く」「ミスが増えている」といった職場で実際に起きている“事例性”にこそ軸足を置いて活動すべきだ、という点です。産業医は、主治医から得られる医療情報を事例性と結びつけて「就業上何が問題で、どのような支援や配慮が必要か」を翻訳し、会社・職場・本人をつなぐパイプ役として機能することが重要であると述べました。
その後のディスカッションでも、精神科医の先生方からは「事例性の情報を共有してもらえると、主治医として就業否や配慮内容を具体的に検討しやすくなる」とのコメントがあり、産業医からの情報提供書記載におけるポイントや「薬を飲みながら働くこと」と「安全配慮」「公平な評価」をどのように両立させるかについて、活発な意見交換が行われました。
今回の講演会を通じて、最新のうつ病薬物療法に関する知識だけでなく、精神科医・産業医・企業それぞれの立場が「事例性」を共通言語として連携することの重要性を改めて感じました。明日からの面談や職場支援に直結する多くのヒントを得られる有意義な時間となりました。

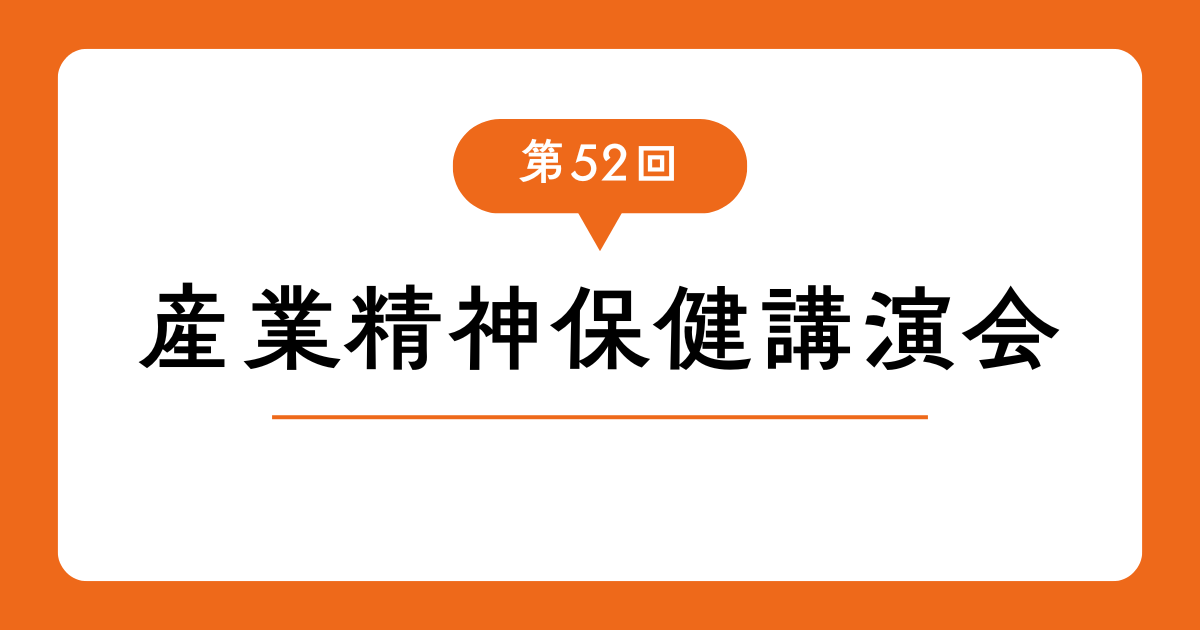
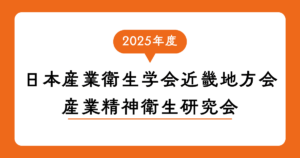
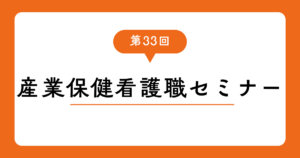
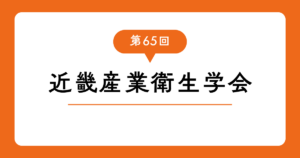
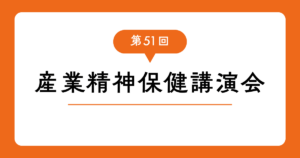
コメント